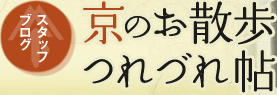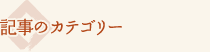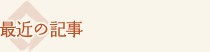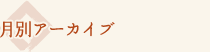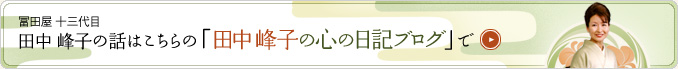2008年1月14日 13:12
黄檗山萬福寺



宇治にある萬福寺さんへのてくてくです。
JR奈良線「黄檗」駅で下車、5分ほど歩くともう萬福寺の門前に到着。
このお寺は江戸時代に中国から渡来した隠元禅師が1661年に御水尾法王や徳川四代将軍家綱の援助を受け開創した黄檗宗の大本山です。
建造物が中国明代の様式であるだけでなく仏教儀式も中国明代のものを継承し毎日のお経も唐音で発音されているとか。
総門から三門へは龍の姿とうろこをかたどった石畳がカギ型につづいています。
山門をくぐると辺りはすっかり中国風!
そこから先は伽藍が龍の石畳によって一直線に並んでいます。
最初は天王殿です。ここには弥勒菩薩の化身といわれる金色の大きな布袋様が祀られていますが、この布袋様は都七福神の一つに数えられています。
今日も新春の都七福神まいりの人がちらほらです。
(どうして判るかって?
それは、皆さん七福神の御朱印が押された大きな色紙を持ったはるからです!)
案内の矢印に沿って長い廊下を進みますが、天井からは中国風のランタンの様な灯籠がいっぱいぶら下がっていて独特の雰囲気です。
途中時を知らせる為の巨大な開板(魚板)があり横にはバットのような棒が置いてありました
本堂や開山堂の前のてすりは卍や卍くずしの形でますます中国風!
萬福寺は普茶料理でも有名ですが、いただくのは次回にして・・?お参りの後静かな境内をゆっくり巡り、最後に布袋様の御朱印を頂いて帰りました。
今回行かなかったのですが、塔頭の宝蔵院に鉄眼和尚が17年もの歳月をかけて彫ったという一切経の版木があり現在でもそれを使って一切経が刷り続けられているそうです。
又、この版木は400字詰め原稿用紙の基になり、その字体は明朝体のもとになっているのです。
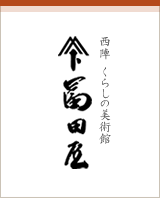
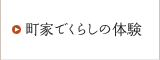
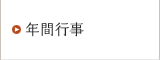
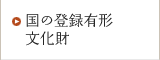
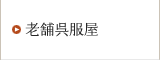
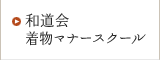

![[ブログ] 冨田屋十三代目 田中峰子の心の日記](/ssi/img/banner_pre.gif)
![[ブログ] 冨田屋と京都の話 京のお散歩つれづれ帖](/ssi/img/banner_staff.gif)